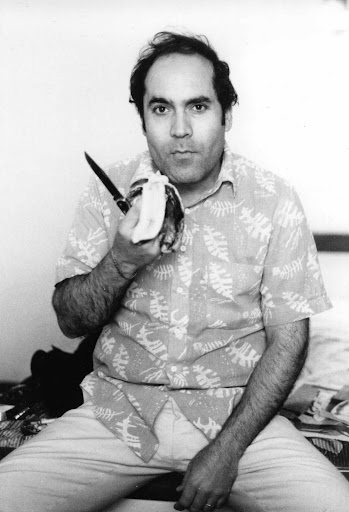昨年、メキシコから帰ったときに書いて『
Latina』に送ったボツ記事。なんかムカツクからパソコンの奥に放っておいたんですが、もったいないから載っけます。環境とかエコとか最近の話題も盛り込んだ面白い記事だったのになぁ。以下記事です。
久しぶりにメキシコシティへ行ってきた。じつに14年ぶり。ちょうど前回帰国する頃通貨ペソがデノミする直前で、盛んにそのお知らせがされていたから、現在の紙幣や貨幣は私には初めてで、物を買う度にあらためてこれはいったいいくらなんだろう?と考え直さなければならない始末だった。
セントロには、
セブンイレブンや
スタバや
マクドが当たり前にできており、夜中や日曜日にはすべて店が閉まってしまったかつてとは隔世の感。こうした外資系のチェーン店の他にも、メキシコブランドのファミリーレストランも、通りに一つといった感じで増えていて、昔よく学校の帰りにお昼ご飯を食べたごくごく庶民的な定食屋も、小ぎれいなレストランに変わってしまっていて、少し寂しく思った。
今回は、"
死者の日"に合わせて行った。ちょうど日本のお盆にあたるようなこの日には、骸骨の人形やお菓子を飾って死者を弔う。ソカロには舞台が出てマリアッチの楽団の演奏し、何万という人の波が夜遅くまで押しかけていた。前月の末に見舞われた洪水の被害で、南部にあるタバスコ州にあるビジャエルモサでは、何十万という人々が避難しているという
ニュースが新聞やテレビで連日報道されているのが、同じ国のこととは思えないような光景だった。
そうしたお祭りの日々が一段落した日曜日、本紙でもお馴染み、チャリ好きでも知られるメキシコシティ在住のライター
長屋美保さんに誘われてサイクリングに行った。事前に長屋さんから話しを聞いていてはいたものの、メキシコシティと自転車というのが、あまり結びつかず、サイクリングというのにさらにピンと来ないまま、早朝の約束の時間に
アラメダ公園へと向かった。だんだんと寒さを増していくメキシコシティの朝の空気はとてもきれいで、ベジャスアルテスや、周辺の建物もみな輝いて見える。しかし、空気がきれいなのは当然で、なんとメキシコシティを東西に走る大通りレフォルマが通行止めになって、自転車と、歩行者の専用道路になっている。すでに自転車に乗って気持ちよさそうにその道路を走る人たちがいる。アラメダ公園には、テントが一つ立てられていて、数人の人がそこらへんに座りながら、何を待つともなく、待っていた。「ここで自転車借りれるの?」と高校生くらいの女の子に訊くと、そうだというので、私たちも待つことにする。9時から、自転車が借りられることになっていて、私たちはそれよりずいぶん前から待っているのだけれど、その9時は当たり前のように過ぎ去っている。なんとなく待つ人が増えてきたなって思ったら、あっという間に列になったので、私たちも慌てて列に加わった。
身分証明の代わりにパスポートを預けて借りた自転車は、マウンテンバイクもどきのメキシコ製自転車で、変速ギアは付いてはいるものの、かなり重いところで固まって動かない。ブレーキも甘いし、空気ももう少し入れたいところだけれど、まぁ仕方ないということで、出発。車の通行が規制されているのは、レフォルマだけではなく、大聖堂や大統領府が並ぶ、ソカロを中心とした歴史地区全体が歩行者と自転車に開放されており、私たちは普段車と人混みと格闘しながら歩いている道を、大統領府の裏側、メルセあたりまで行ってUターンする。アラメダ公園まで帰ってきて、今度はベジャスアルテスの裏手、北側のイダルゴを通ってレフォルマに入った。
それからは、メキシコ一番の大通りを独り占めにしているような爽快な気分で、
地下鉄クアウテモク駅あたりまで。折り返して再びアラメダ公園まで戻ってきた。約1時間半ほどの行程だったが、排気ガスが有名だったこの町が年月とともに変わりつつあることを実感し、これまでとは文字どおり、違った角度でメキシコシティを眺めた時間だった。
後日、なにげに町をぶらついていると、ソカロの片隅に、「
チャリで行こう」と書いたブースがあり、自転車のレンタルとプロモーションをしていたり、
NHという高級ホテルの前には、私たちが借りたおんぼろな自転車ではなく、まだ真新しい自転車が並べられているのを見かけたりと、どうも町を挙げて、自転車を推奨する運動中であるらしいことがわかった。
帰国後さらに調べてみると、この運動は、
メキシコ市の環境局が中心に進めており、日曜日にレフォルマへの自動車進入を規制して歩行者天国にするのは、この一連のプログラムの主軸であるらしい。もともと、昨年12月に就任した
マルセロ・エブラルド市長の前職で、現在の
フェリペ・カルデロン大統領との大統領選に僅差で敗れ、現在でもその正統性をめぐってしばしば市民の抗議行動も見られる
ロペス・オブラドール氏が市長だった時代に立案された政策で、環境や資源、市民の健康など私たちが抱えているのと同じ問題を持つメキシコ市がその解決策として始めたことだ。前職と同じ左派の
PRDに属するエブラルド市長になっても、この政策は継続され、今年3月にこの政策の継続とその目的を新に説明したプログラムを発表している。それにしたがって、メキシコ市は、自転車専用道路を整備し、自転車をレンタルしたり、メンテナンスや水分の補給を目的としたブースを設置しており、バスや地下鉄への持ち込みも実験中で、それらを乗り継いでの通勤も推奨されている。政府の関係者には毎月第1月曜日には自転車の通勤を義務づけて、市長自ら自転車通勤している。この4月から始まったこの規則のことを当時の新聞で調べていると、休暇で逃れようとした議員が後で叩かれたりしていて、最近はどこの国の議員も監視が厳しくたいへんだ。私が、たまたまホテルの前で見つけた自転車も、メキシコ市から市内の
ホテルに贈られた250台の自転車の何台だったようだ。ホテルには、自転車で市内を廻るスポットを載せたマップもあるようなので、観光で行く予定の方はぜひ試してみてみると興味深いと思う。
今年の<自転車天国>のスケジュールは
ここに載ってます。去年記事を書くときに見つけた素敵なブログ、"
Ciudad en Bicicleta"は、世界中での町で自転車がどう受け入れられつつあるかの情報をスペイン語で提供してくれています。著者はメキシコのグァダラハラの人なので、やはりメキシコの情報が詳しいです。